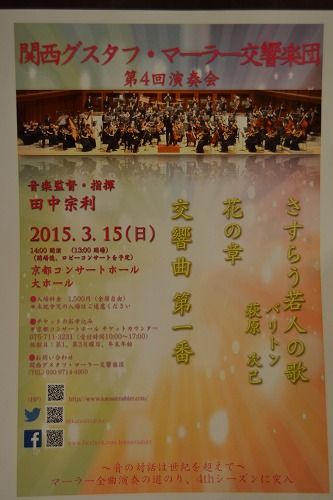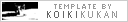2015.05.28
5月28日(木) / ローズ ポンパドゥール・ひみつの庭の“ママの日”だより(5/26記録)・園内通信
*************************
<ローズ ポンパドゥール> 2009年 フランスGeorges Delbard 社作出
*************************
長い間咲いてくれている庭のローズ ポンパドゥール。少しずつ、花の重みでうつむき加減に咲く魅力的なバラの一つ。カップ咲きからロゼット咲きに変化しながらフルーツ香を漂わせています。色、形、香り、強さと、四拍子揃ったとても扱いやすいバラです。
* * *
5月後半。真夏日のような日々が続いていますが、子ども達はとても元気に過ごしています。この5月は各クラスを訪問し、子ども達と園庭で過ごす時間が増えました。季節のよい5月は、距離の違いはありますが全学年が園庭つづきのひみつの森へ度々足を延ばしています。
鳥の声に耳を澄ませながらバードコールを使ってみたり、鳥の声のように美しい口笛を鳴らせる年長児Rくんが鳥を呼んでくれたり・・・。子ども達にとって、一番身近である自然の中に身を置く体験が例年以上に増えました。特に年長クラスは森から清沢へ下りて思いっきり水と戯れたり、また斜面を滑り下りたりよじ登ったり。過去に私が小学生しぜんクラスの子ども達と自然体験していた場所を訪れ、また新たな場所を求めながらダイナミックな活動をしています(臨場感あふれる様子をお伝えできるとよいのですが^^)。
つい先日25日(月)は、清沢へ一旦下りてから再び川をさか上り、東山トレイルの途中にある〔白幽子巌居之蹟〕まで辿り着きました。その周辺で思いっきり遊んだあと、東山三十六峰の一つ茶山経由で園庭まで戻るルートを楽しみました。9時40分に園庭をスタートして12時前に園に戻る約2時間コースは、約50人での新体験となりました。私自身、園庭つづきで巌居之蹟へ至るコースは何度も歩いていますが、川をさか上るルートは初めての試みでした。私と一緒に先頭を務めてくれた冒険心たっぷりの男の子グループと、途中見えてくる案内板の図を確かめながら浅瀬の渓流を上り詰め、想定通り現地に到着したときには嬉しい達成感がありました。ともに冒険の心持ちです。いつもは園庭つづきのルートで巌居之蹟まで歩きますが、今回はそれよりも10分ほど早くつくコースを子ども達と辿ったことになります。
大変健脚で体力が尽きない元気な子ども達。そんな子ども達と森の中を駆け巡るように過ごせる活動は、私達にとって新たなチャレンジ体験でもあります。屋外での体育あそびや自然あそびを存分に体験しながらますます元気に過ごしていきたいと思います。
----------
ひみつの庭の“ママの日”だより(5/26記録)
今週の26日(火)は、エール株式会社の瀬川さんにお出でいたただき各学年の体育指導をお願いしていましたため、この日、ママの日の活動はお母さま方にすっかりお任せする形になりました。


早速お出で下さったママが入口シンボルツリーの辺りの草抜きを始められました。こちらのサークルスペースは子ども達が常時足を踏み込む場所になります。種を蒔いても元気に生えそろう可能性は低いので、再度芝生のターフを後日植えていただくことにしました。


小型の熊手を使ってお手伝い中の未就園児Jくん。陽射しが真夏並みなので首元を直射日光から保護することはとても大切ですね。しっかりと垂れつき帽子を被って活動中です。お母さまの手元をよく見ながら思案中でしょうか。


北側のメキシカンセージのコーナーを草抜きをして下さるYママ。別名アメジストセージまたはベルベットセージとも呼ばれます。日本では秋に入って咲き始め、霜が降りる頃には地上部は枯れ、地下茎で冬越しします。毎年、紫色で草丈1.5mほどで大型の花を咲かせてくれるので今年の秋がまた楽しみです。次は固くなった土をほぐしながら、水分や酸素が取り入れやすい柔らかい土にしたいと思います。草抜き後はコンポストへ運んで下さいました。
コンポスト前には木製の柵を設置しました。この春、夜間に森からやってきたイノシシがコンポストの腐葉土に目をつけたらしく、まるでブルドーザーで掘り返したように一時期荒らされたことがありました。なので、イノシシ除けの柵を作っていただいた次第です。タケノコが芽を出す時季にはイノシシの活動が活発になります。柵を設置して以降は大丈夫です。


ビオトープエリア。Tママはビオトープに入り発生した藻を取って下さいます。Iママは横の植え込みの落ち葉をきれいに取り除いて下さいました。Jくんはお姉ちゃんのMちゃん発見!親子ご対面の嬉しい瞬間。


ビオトープは現在のところ、メダカがたくさん育っています。またタナゴは25~30匹ほど、ゲンゴロウブナが5匹ほどが見られました。ビオママ(ビオトープに詳しいSママ)のお話では、3月から正に今がゲンゴロウブナの産卵期だそうなので、岸部の植物などに産卵していないかと時折のぞいているところです。ゲンゴロウブナ(琵琶湖固有種)は雑食性ではなく草食性のフナ。ビオトープの中の藻を数匹でゆっくりと食べている姿を先日見せてくれました。しかも中の一匹のお腹が少しふくれていたように思えたので、初の産卵が見られることに期待!
年長児の女の子Sちゃんが見せているのは四つ葉のクローバー。四つ葉クローバーが比較的生えやすい場所があり、四つ葉が連続で見つかることもあります。そんな時女の子達は大喜びしています。
----------

こちらは昨日27日(水)の午前中。全園児半日外遊びの時、ビオトープに遊びにきた子ども達の様子です。子ども達と一緒に活動しているとなかなかカメラで撮影はできません。男の子がカエルを捕まえたり、大きくなったヌマエビを手の平に溜めた水で泳がして観察したり、また年長児Sくんが藻を一緒に取ってくれたりと、とても賑やかな夏の水辺がスタートしつつあります。近いうちにオタマジャクシがたくさん見られるようになりそうです。モリアオガエルもそろそろ森からやってきて、ビオトープの付近に白い泡のような卵を産卵する頃です。
----------
本日は、園内通信「お知らせ25」をお出ししました。
内容は、
◇ 短冊(七夕製作)を入れる箱について
◇ 出席カードの平熱のご記入について