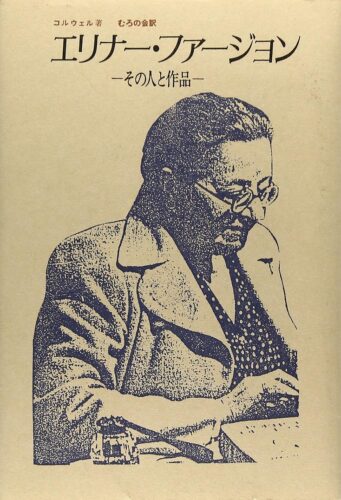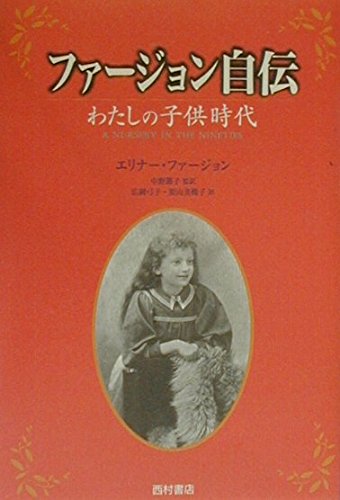
福西です。
以下は、私が以前に書いた文章です。ことばを記録すれば、過去から力を取り出すことができます。山の学校の「ことば」クラスでは、そのようなことばを大事にしています。受講を検討される方の、ご参考になれば幸いです。
『思い出は力になる』 福西亮馬
ある時、ふと気が付いたことがあります。それは、「児童書の作者は大人である」ということです。当たり前ですが、私にはハッとなった事実でした。子供が児童書の作者になることはできない、というのは。もちろんそれは誤りの多い表現かもしれません。けれども私が思うに、仮に子供が書いた児童書というものがあって、それがもてはやされたとしても、残念ながら、その後に生まれてくる子供たちの眼からすれば、読み継がれる古典、彼らが大人になった時に思い出せる源泉にはならないだろうと思います。
なぜなら、児童書の題材となる出来事は、子供時代を「今」過ごしている者には近すぎるからです。絵でいえばカンバスからはみ出すぎて何の絵の一部なのか分からない、そのように「今を今」として描くことしかできないからです。
児童書の作者に限らずとも、本当に胸を張って子供と接することのできる人は、子供時代を忘れない人だと思います。ですので、ここでは「忘れずに思い出すことのできる者」という意味で、「大人」という言葉を使います。すなわち書くことでそれを試みる児童書の作者もまた「大人である」というのが、私には真新しい発見でした。
そしてそのうちに、児童書を読む意義は、「思い出すことを学べること」(大人になれること)なんだ、という考えが浮かんだのでした。
ところで、私と児童書との本格的な出会いは、大学生で家庭教師をしていた時に偶然やってきました。ここでは割愛しますが、それが出会いであって再会でないのは、子供の頃にまともに児童書を読み込んだという記憶がなかったからです。おそらく当時の私の感覚では、名作と呼ばれる本はどれも「字の多い」ものとして避けていたのだろうと思います。子供の時期に、こっそり読んだ宝物がないというのは、本当にもったいないことだと思います。逆に何か一つでもそれがあれば幸せだと思います。
私にとって、遅ればせながらのそれは、『リンゴ畑のマーティン・ピピン』(ファージョン、石井桃子訳、岩波書店)でした。その一冊を皮切りに、彼女の作品に夢中になりました。そして、作品ににじみ出る「現実を肯定する力」は、どこから湧いてくるのだろうと、ファージョンの人となりに興味をおぼえました。

(リンゴ畑のマーティン・ピピン)
ファージョンの伝記を読むと、TAR(テディー・アンド・ラルフ)という自分たちでこしらえた「空想ごっこ」をしていたことが書かれています。一家で芝居を見に行った後に、兄のハリーが、妹である彼女に言い出した遊びで、芝居の役(テディーとラルフ)になりきって、即興で「続き」を演じるというところから始まったのだそうです。その遊びには日増しに工夫が重ねられ、いつしか、なくてはならないものへと、「TARがないのは魂を取られるようなもの」だと嘆くほど、ファージョンにとって大切なものになっていきます。「さあ、TARをしよう!」と兄のハリーが言った瞬間、子供部屋はたちどころに物語の舞台になります。
TARは、現実逃避とは違って、むしろ現実を支える力を持っていました。もっと言えば、現実に対する自分の在り方を変えられるという、積極的な意味合いがありました。そのような、しなやかな自己肯定に支えられたファージョンは、誰かが現実を変えてくれるのを待つより、その見方を変えます。すると、現実の舞台の袖にそれまで見えていなかった俳優たちが見えてくるようになったのです。
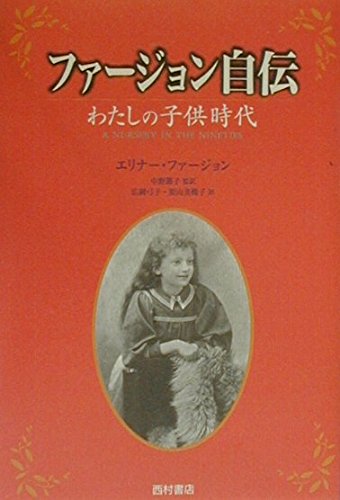
(エリナー・ファージョンの自伝)
ファージョンにとっての「物語ること」とは、過去の自分が見ていたものをもう一度再現すること、あるいは作り直すことだったように思えます。それを彼女はTARで磨いたのではないかと。名優の演技は人を勇気づけます。それこそが彼女の作風だったのです。私が本屋で何気なく見つけた『リンゴ畑のマーティン・ピピン』にたちまち虜となった理由はそれだったのです。
将来を思い悩む時、それを描けずに行きなずむことがあります。未来は曖昧だからです。けれども過去は確実です。ただ未来に何をしたいのかではなくて、過去の自分が何をしたかったのか。あるいは、過去の自分が、未来の自分に何をさせたかったのか。もしそれを思い出せたのなら、それは今こそ必要なヒントとなります。そのように、思い出は力になります。未来はそうやって過去のうちに眠っているのだと思います。
思い出すこと。それは旅の計画のように、きちんとした元手のいる作業です。「旅がしたい」と言ってもなかなかできないように、言うほど生やさしいことではありません。もしかすると一生に一度あるかないかの機会で、それを逃すと二度と巡ってこないのかもしれません。思い出されたものがいいものばかりとも限りません。意味のない、涙も枯れてしまいそうな経験がまた蘇ってきてしまうかもしれません。でも、人の不思議さというのは、自分の歴史の一部に「触れた」と感じた時、その感触を力に変えられることだろうと思います。
いつか自分が新しい局面に対して、もっと力を欲しくなった時。その時のために、せいいっぱい書き残しておくこと。私はそれが大切だと考えます。冒頭で述べたように、「時間が離れていなければ書けない」という難しい問題はあるにせよ、何も今すぐ作品のような完成度を持つ必要はありません。
大事なのは、「今はメモでいい」ということです。
そのとき感じたことは、すぐ書き留めておかないとその事の意味が薄れてしまうので、ひとまず急いで書き留めておく。それは二、三行のこともあれば、一ページあるいは数ページに及ぶこともある。
こうしておけば、あとはほかのたくさんのアイディアと一緒に、本や書類の積み上げられた机の上に、ずっと放っておいても大丈夫。すっかり忘れてしまったように見えるけれど、このようにまいておいた作品の種は、どんなに時間がたってから取り出しても──一ヵ月後、あるいは一年後でも──たいていの場合、知らない間に大きく育っていて、詩や物語となって実を結ぶものである。
──コルウェル著『エリナー・ファージョン』(むろの会・訳、新読書社1996年)より、ファージョン本人の言葉として。
(福西亮馬)