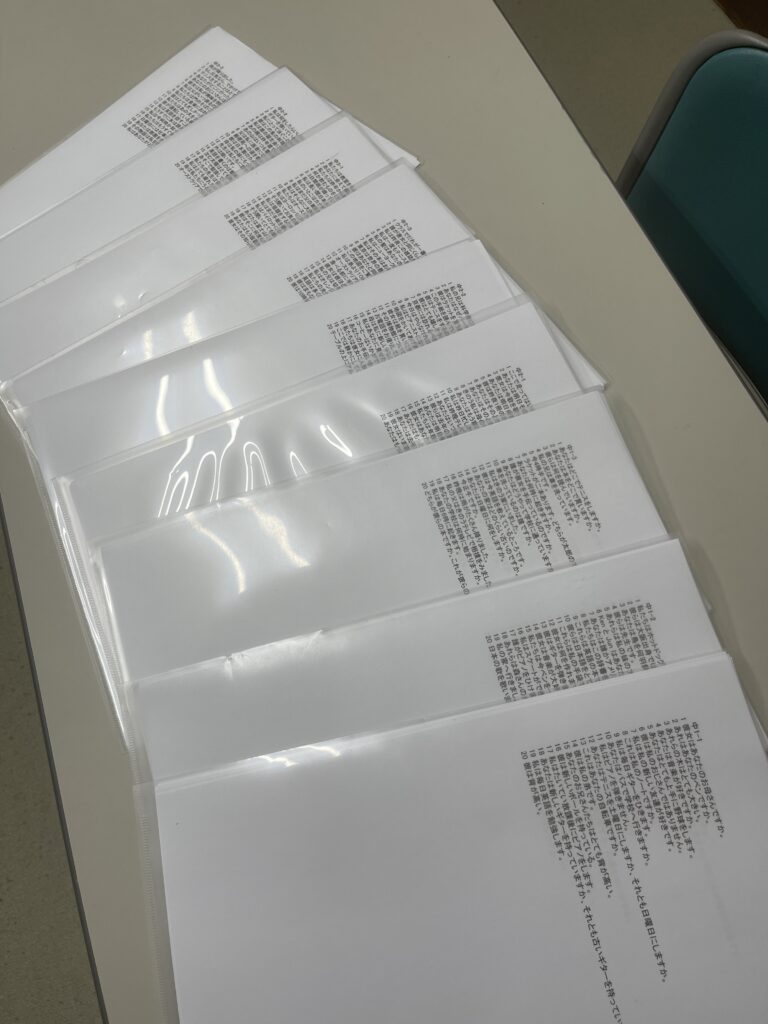山下です。
いつものようにひとり一人自分の課題に取り組みました。
1年生は2学期に入ったので、2学期の課題に取り組み出しました。
1学期の課題は数えきれないほど繰り返したので、日本語を見たらすぐに英語が浮かび、正確に書ききることが出来ています。
「できる」という基準が身に着いたことが何より大事だと思います。
あとは、2学期になっても、3学期になっても、2年になっても、3年になっても、「今のできるという感覚」でできているかどうか、自分で判断できるからです。
案の定(だれがやっても当然そうなりますが)、はじめて取り組む二学期の課題は最初は手こずります。
鉛筆の動きがとまると、私はその都度助言します。自分で辞書を引いて解決しようという生徒もいます(えらい!)。
二年生になると学校の宿題も気になるようです。
私の課題を1,2枚こなすと「宿題をしていいですか?」と言って取り組みます。
公立中学のざらばん紙の課題は大事なポイントを厳選して取り上げています。
「日本文に合うように空所を埋めなさい」という問題や並べ替えの問題が続きます。
私は生徒に言いました。「それぞれの問題の答え合わせができたら、その『日本文』だけを見て英語を書きなさい」と。
「わからない場合正解をみてもよろしい。ただし、何度も書き写して覚えましょう」と。
学校の問題集の課題のまるつけをして終わりにせず、その日本文→英文を繰り返したところ、本人も驚くほどすらすらできるようになりました。
「これを全範囲にわたってやればよい。次の試験が楽しみになるよ」と。
生徒にとって学校の課題や試験が切実な意味を持つ場合もあり(ふつうはそうです)、といって、学校の課題の答え合わせだけをさせておくわけにもいかず、昨日はこのような指導をしました。