
講演会「古典の夕べ」リポート
『ギリシア文学の国際性、今むかし』
講師:中務 哲郎(日本西洋古典学会委員長・京都大学文学部名誉教授)
以下は2015年2月21日に行われた講演記録です。
中務先生は、西洋古典研究に生涯を捧げてこられました。京都大学文学部の名誉教授で、現在は日本西洋古典学会の委員長をされています。故松平千秋先生、故岡道男先生の衣鉢を継がれ、『イソップ寓話集』(岩波文庫)をはじめとするギリシア・ラテン文学作品の多数の翻訳や監修、西洋古典叢書(京都大学学術出版会)の編集委員をされてきました。昨年『ヘシオドス全作品』(京都大学学術出版会)により第65回読売文学賞(研究・翻訳賞)を受賞されたことは記憶に新しいところです。
講演の冒頭で、中務先生は、西洋古典を志すきっかけとなったご自身のエピソードをお話してくださいました。片岡桂子先生という、中務先生の中学生時代の担任の先生がおられます。その恩師のもとに、中務先生が大学を出たことを報告しに行かれた折、ある一つの物語をお聞きになったそうです。当時、夜間中学に転じておられた片岡先生は、戦争で教育の機会を失った人たちのクラスを受け持っておられました。そこに通っておられた年配の方が、こうおっしゃったそうです。「『太陽』という漢字を初めて習った、その次の日から、太陽が違って見えた」と。そのエピソードを、中務先生は次のように解釈されたそうです。「物の見方が変わるような勉強をしなさいよ。それは学校にいる間だけではなくて、これからもずっと必要になるものですよ」と。それを恩師からのメッセージだと受け止め、今日に至っているということでした。
このたびの講演では、「古代ギリシアにおいて、ギリシア文学がすでに国際的だった」ことをテーマにお話しいただきました。そして、その国際性が実現するプロセスと、影響のあった箇所とを、文献に残る具体例を通してご教示いただきました。
最初の内容は、文化(物語)の移動、国際化のプロセスについてでした。「文化」と聞くと、たとえばアレクサンドロス大王の東方遠征のように、大移動のイメージが真っ先に思い浮かびます。ですが、実際にはもっと小さなレベルにおいても集団の移動と融合とがあちこちに生じていただろうということでした。その小さな集団の例として、中務先生は、ヘーロドトスの『歴史』(1巻164、94、110~116章)から、ポーカイア人と、サウロマタイ人の縁起の部分を引用されました。ポーカイア人は戦争によって移動を強いられた例で、サウロマタイ人(の祖となるリュディア人)は、飢饉によって移動した例でした。
仮に、五十人規模の軍隊が移動するだけでも、それに付随する酒屋、料理人、小売店など兵士相手に商売をする人とその家族も移動することになります。その中から言葉をすぐに覚える人も現れれば、物語の好きな人も混じっています。そうした人たちを介して、物語に代表されるような文化が移動していったのではないか、というお話でした。すなわち、小さな集団が奇遇する場では、本能的に同じ物語を、繰り返し聞いたり語ったりすることが好まれ、その結果として、異なる文化の中に同じ種が蒔かれ、時にはその民族のアイデンティティーを示すような物語(後で見る旧約聖書など)の枠組の中にも、共通のモチーフが浸透していったのだろうということでした。
次の内容は、ギリシア文学の国際的な影響についてでした。その例として、中務先生は、ホメーロスの『イーリアス』とアポロドーロスの『ギリシア神話』を引用され、その中にある二つのモチーフが、(文字による成立が)時代的に少し後になる『旧約聖書』の中にもはっきりと存在することを示されました。一つは『わざわいの手紙のモチーフ』、そしてもう一つは『パイドラー・モチーフ』と呼ばれるものでした。
『イーリアス』(6巻152~)には、トロイア方のグラウコスと、ギリシア方のディオメーデースとが、先祖同士が昵懇だったことを知り、矛を取り下げ、武具を交換して別れるというくだりがあります。その先祖を語る部分に、ベレロポンテースという英雄が登場します。そのベレロポンテースの物語の中に見られるのが『わざわいの手紙のモチーフ』と呼ばれるもので、それは以下の通りでした。
ベレロポンテースは、過って身内を殺めた罪を清めるために異国のプロイトス王のもとに身を寄せています。そのベレロポンテースに、プロイトス王の妻であるアンテイアが懸想をします。しかし彼女は自分の思いが遂げられないと知るや、夫にこう讒言します。「ベレロポンテースが嫌がる私を無理矢理に辱めようとしました」と。プロイトス王は怒り、ベレロポンテースを殺そうとします。ただし、当時のギリシア人のモラルから、異国からの客人は神様の化身かもしれないので、直接手をかけることは憚られます。そこでプロイトス王は、親戚である王に手紙を届ける役目をベレロポンテースに言いつけます。(作者とされるホメーロスは文字を知らないことになっていますので、この手紙は「印」であるということでした)。ところで、その手紙には「これを持参した者を殺すべし」という意味が込められていました。ベレロポンテースはその危険な手紙を携え、何も知らずに使いに立ちます。そして相手方の王はその手紙を見るなり、彼を殺す方便として、キマイラという三体合体の怪獣の退治を命じます。(この後のベレロポンテースは、神助により有翼の馬ペーガソスにまたがってキマイラを倒しますが、その後も彼の運命は転変します)。
そして、上の『わざわいの手紙のモチーフ』が、『旧約聖書』(サムエル記下11)にも見られることを教えていただきました。プロイトス王の役回りがダビデでした。彼はウリヤの妻バト・シェバと不義を交わし、彼女が自分の子を身ごもったことをごまかすために、ウリヤを戦いの前線から呼び戻します。しかしウリヤは自宅には立ち寄らず、ダビデの思惑は外れます。そこでダビデは不義を隠すことをあきらめ、ウリヤを殺す方法を記した命令書をウリヤ自身に持たせて、前線の司令官に送ります。ウリヤはそれがために死んでしまいます。聖書学の方では、これを『ウリヤの手紙のモチーフ』と呼ぶそうです。最終的に文書の形に纏められたのは『旧約聖書』の方が『イーリアス』よりも新しいけれども、物語としては『旧約聖書』の方が古く、それが何らかの経路をとってギリシアに伝わったのではないか、ということでした。
中務先生は、次に『パイドラー・モチーフ』を紹介されました。このモチーフは文字通りパイドラーの物語がその典型となったもので、先のベレロポンテースに懸想したアンテイアと同じく、「人妻の誘惑」という型です。アポロドーロスの『ギリシア神話』(摘要1.18~)から引用されたエピソードは、以下のようなものでした。
パイドラーはテーセウスの後妻でありながら、養子のヒッポリュトスに恋心を抱いてしまいます。しかしヒッポリュトスから拒絶されると、彼女はテーセウスに讒言します。そこでテーセウスがヒッポリュトスの破滅をポセイドーンに祈り、ヒッポリュトスの死につながるという展開です。そして、この類話がまた『旧約聖書』(創世記39)の方にもあり、『ヨセフとポティファルの妻』のエピソードとして伺えるということでした。
面白いことに、この二つのモチーフは人々が好んで繰り返し語ったようで、たとえば『わざわいの手紙のモチーフ』の方だと、近代西洋においては『ハムレット』に入り、遠く日本の物語でも『宇治の橋姫』に現れるとのことでした。そして中務先生は、柳田國男が『遠野物語』でも「此話に似たる物語西洋にもあり、偶合にや」と東北地方の類話に対して註に書いていることを指摘されました。
ところで、小学生の子供たちに私は紙芝居をする機会があるのですが、その時に読んだ『ぬまのぬしからの手紙』(童心社)という紙芝居が、まさしくそれでした。この講演で「それがこれか」と知って目から鱗でした。
講演のレジュメに沿った内容は以上です。その後も、質問の時間をたくさん取っていただき、様々なお話を聞くことができました。
たとえば、これは男性の参加者の方からでしたが、次のような質問がありました。「『ヒストリエ』(岩明均、講談社)というアレクサンドロス大王時代を舞台にした漫画があります。その中で、主人公がギリシア系の植民地にいて、お店の人に、『クセノポーンのアナバシスの最新刊はまだですか』と聞くシーンが出てきます。そのように、ギリシア人は、本国の書物をあちこちの植民地でも読んでいたという国際性はあったのでしょうか」と。その後で、中務先生から『アナバシス』の世界にタイムスリップしたようなお話や、当時の本の流通事情を伺うことができました。
また女性の参加者の方からは、次のような質問がありました。「当時、書くことは石に彫り刻むという骨折り作業だったのに、なぜ人はそうまでして物語を伝えようとしたのでしょうか」と。そこで中務先生は、「人間には過去を記憶しておきたい、同じ話を繰り返し聞きたいという、いわば物語への本能ともいうべきものがあるからなのだろうと思います」と答えておられました。「個体発生は系統発生を繰り返すという説があるように、おそらく人類の歴史にも子供時代があって、同じ話を繰り返し聞くことをむしろ快いと思うような時期だったのでしょう」ということでした。
そこでふとこの講演自体が、もしかすると、実地にそのような出来事だったのではないだろうかと思い当たりました。中務先生は、引用された文章をただ読み上げることはされず、当時の習慣についての記述や、地名や人名といったカタカナの固有名詞が出てくると、そのたびに、「~というのは……」という言葉に続いて、臨場感たっぷりに説明されていました。たとえば、「『アッティカ』というのは、アテーナイというのがギリシアの首都ですが、そのアテーナイを含む地域をアッティカと言います。たとえば京都に対して近畿地方というようなものです……」であったり、「ギリシア人は洒落好きな民族で、『アマゾン』というのは、ギリシア語でマゾスが乳房で、アがそれを打ち消して、乳房がない、という意味です。なぜならアマゾンたちは馬上で弓を引きますから、右側の乳房を邪魔だから自分から切り落としてしまったのです……」であったり。子供がお話の途中で「それは何?」と質問を繰り返すことがありますが、中務先生の語り口は、あたかもその質問に前もって答えて下さっているように感じました。そして私自身、知らず童心に返っていって、人に昔話をせがんでいる時のような温かい気持ちになりました。また、モチーフの共通する物語を重ね合わせて聞いていると、まるで一つの海の前に立って繰り返す波音を聞いているような落ち着きを覚えました。この稿では、その体験に関してあらすじをもって追うことしかできていませんが、もしここまでお読み下さった方には、ぜひともその時じかに聞いていただきたかったと思う次第でした。
他にも、アレクサンドリア図書館や古代の製紙事情のこと、写本や紙背文書の話、印欧祖語のこと。なぜギリシアのような小国がペルシャ帝国に勝つことができたのか、ギリシア人は何を頼みとし、武器にして戦ったのか。それについてのヘーロドトスの言説。また一方では贅沢で滅んだギリシア系植民都市シュバリスのことなど。参加者の次から次へと湧き上がる疑問にも中務先生は即妙に応じて下さり、長時間、多岐にわたってお話をしていただきました。
今振り返るにつけ、大変得がたい貴重な時間だったことに思いが至ります。ありがとうございました。
(福西 亮馬)
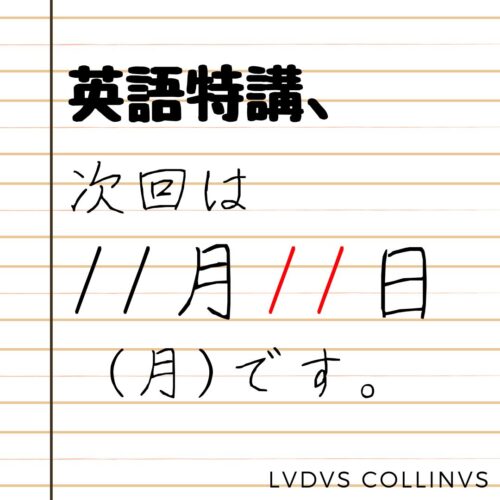
“『ギリシア文学の国際性、今むかし』(「古典の夕べ」リポート2015年2月)” への2件のフィードバック