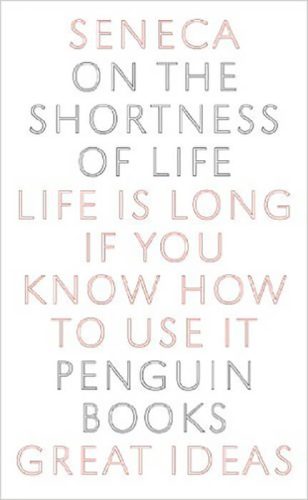
福西です。
残りの時間で、セネカ『人生の短さについて』全体を振り返りました。
野心的に生きること(6,17章)。
刹那的に生きること(7,16)。
多忙に生きること(12)。
互いの時間への侵入を許し合い、互いに利用され合うこと(2)。
そして、自分の時間がいくらでもあるように思うこと(8)。
このような習慣や認識で、人生を短くしている張本人は、他ならぬ自分である、というのが最初の主張でした(1)。
9.1では「ただちに生きよ」(protinus vive)という言葉に出会いました。
そしてこの日もまたその言葉をめぐって、「今を生きる」ということで議論しました。
刹那的な今と、永遠的な今とがあることを考えました。
セネカは、未来で現在を無駄にするなと警告しながら(9.1)、人生の全体像(完成予想図)や死(ゴール)を意識せよと言います(1.3や7.9)。全体像や死は、未来にあります。だからこれは矛盾ではないか? というのが、前々からの疑問でした。
しかしよく考えると、下線部の認識が、間違っていたのかもしれません。
そこで、「今」という時間には、水平と垂直があるのではないかという話になりました。
一つ目は、時間と同じ方向に流れ、未来が過去になっていく「表面」としての今。刹那的、反応的(刺激に対して受動的)なそれです。
もう一つ、時間と垂直に「立つ」今があります。時間が止まっているように感じられる瞬間。それは、永遠的、応答的です。
何に応答するのか? 真上に目線を向けてみます。するとその先には、「理想」が輝いています。理想に対する応答性、それが二つ目の今です。
もしそれがあるとすれば、普遍性(ストア派なら「自然」を掲げることでしょう)に対して、オープンな瞬間でしょう。その気付きを一度でも多くすること。それを、セネカは「毎日毎日を最後の一日と決める」(7.9)「哲学する」「静かな港へ向かう」(18.1)と言っているのだと思いました。人生の全体像や死の認識は、未来ではなくて、永遠に属するのではないか? と考えました。
もちろん理想だけでは足元を掬われるでしょう。でも理想なしでも、「哀れさの中身を変えるだけ」で人生は終わるでしょう。そのように振り返りました。
多忙(occupatus)と暇(otium)。
嵐(tempestas)と凪(tranquillitas)。
人生の短さ(brevitas)の次のキーワードは、心の平静(quies、tranquillitas)です。
というわけで、次回からは、同じテキスト(『Seneca On the Shortness of Life』(C. D. N. Costa訳、Penguin Great Ideas、2005))所収の「On Tranquillity of Mind」(心の平静について)を読みます。
以下、そのPRです。
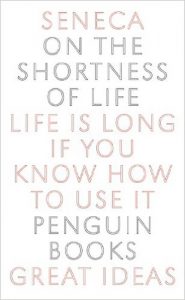

セネカ『心の平静について』は、「もし何か薬をお持ちなら」ということで、セレヌスという人がセネカに不安を相談するところから始まります。「自分のこういうところが嫌で、くよくよするんです」と。今でいう「お悩み相談室」の乗りです。そこで、セネカが出した(言葉の)処方箋は、「自分に信頼し、自分は正道を歩んでいると信ずる」(茂手木訳2.2)ことだとあります。
セネカは、セレヌスの症状に対して、「十分に健康でないのではなくて、十分に健康に慣れていないのだ。」(茂手木訳2.1)と言います。「あなたの心は十分健康です。それについて十分自覚がないだけです」と。これには、『人生の短さについて』でも見た「人生は十分に長い」の逆説を連想します。
いろいろなメディアを通じて、健康法やら勉強法やらで、「あれがないから」「これがないから」と不足を訴えられると、つい不安になってしまう現代人にとって、ふさわしい切り口だと思います。
もし技術が進歩しても、人間があまり変わらない生き物なのだとしたら、現代的な視点のみでとらえるよりも、昔からの普遍的なケースとしてとらえなおす方が、隔靴掻痒の問題を解きほぐしやすいのではないでしょうか。
ご参加をお待ちしています。
